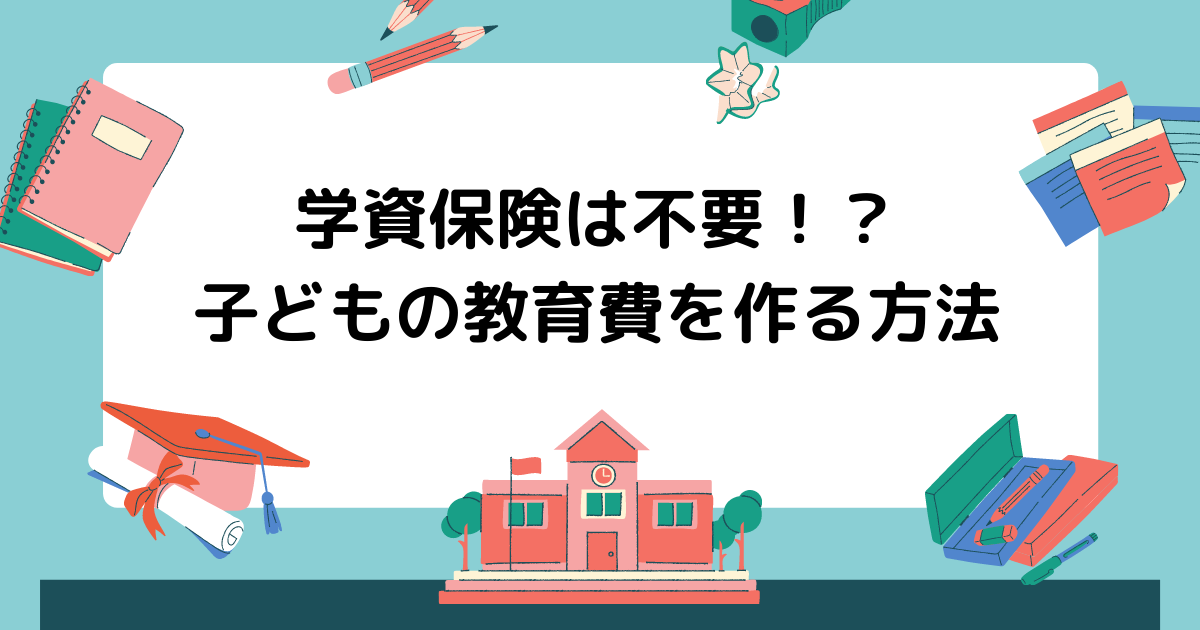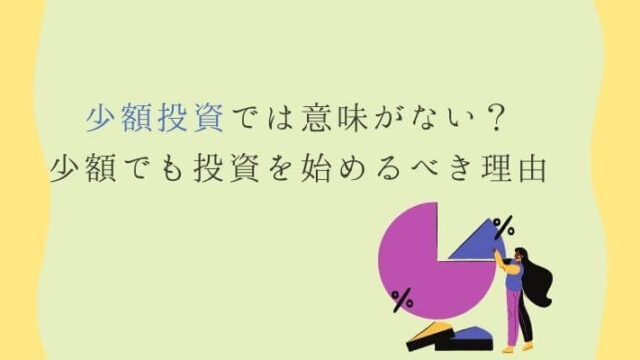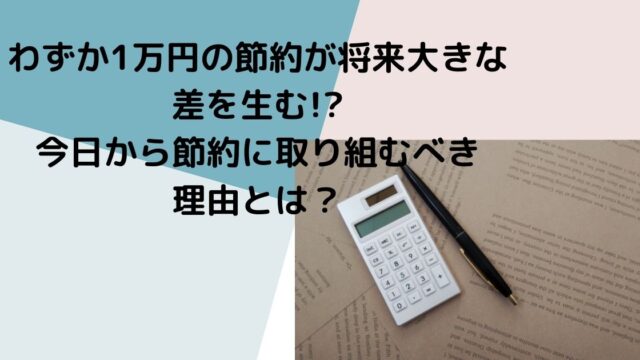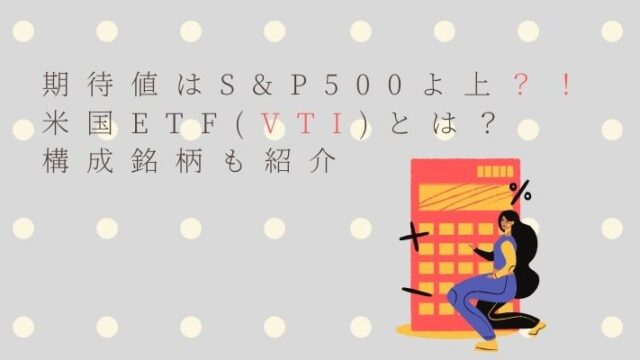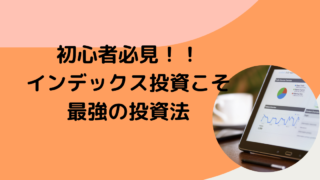大学卒業までにかかる費用
子どもが生まれると考えるのが将来の為の教育資金作り。
文部科学省の調査によると、平成26年度の国立大学の授業料は、
年間約54万円(入学金約28万円)で私立大学に至っては、年間約86万円(入学金約26万円)となっています。
つまり、国立大学に入学し卒業するまでにかかる費用は約244万円。
私立大学は370万円がかかる計算になります。
もちろんかかる費用はそれだけではありません。
その他、受験料や初年度の学校納付金、通学にかかる交通費、下宿をする場合にかかる引っ越し費用やアパートの敷金・礼金、家財道具の準備にかかる費用大学を複数受けた場合の併願校への納付金更にはなどもかかってくる。
これらはあくまでも一般的な大学費用の一例であり、大学によっても金額も変わってきますし、学部や学科によっても変わってきます。
市立大学の医学部になると6年間で2,000万円を超えると言われていますので一概に上記の金額で収まるわけではありません。

学資保険で元本割れする事態が発生?!
これだけの金額をいきなり準備するのは非常に難しいので将来に向けて学資保険を活用されている方も多いのではないでしょうか?
学資保険の最大の特徴は、契約者に万が一の事があった場合、それ以降の保険料の支払いが全額免除され、お祝い金や満期保険金は契約時に定めた通りに支払われる点です。
学資保険と言うだけあって保険としての機能もありますのでそこに安心して始める方も多いのではないでしょうか?
ただし、混ぜるな危険!と言う言葉があるように保険と投資を混ぜて考えてはいけません。
あくまでも投資を含んだ契約プランになっていますので元本割れのリスクを含んでいます。
実際、日本の低金利の影響で返戻率が100%を割っている学資保険も出てきているので注意が必要です。
つまり、学資保険で積み立てた金額の元本割れする事態が発生しているのです。
また、保険会社が倒産する可能性もあります。
せっかく積み立ててきた保険が無くなる可能性もありますし、倒産したら銀行のように預貯金の保護もありません。
実際に過去に10社程度の会社が倒産しています。
これらを総合的に判断して学資保険に加入するかを決めた方がいいと思いますので学資保険のメリット・デメリットについても述べていきたいと思います。

学資保険のメリット
1. 契約者に万が一の事があっても、それ以降の保険料の払込が全額免除され、お祝い金や満期保険金は契約時に定めた通り支払われる。
2. 所得税のかかる保険金では、利息分が50万円まで非課税になる。
保険金を一括で受け取る場合一時所得になり、年金方式で受け取ると雑所得になる。
一時所得には、特別控除があり最高50万円まで非課税になる。
※契約者と受取人が別人の場合は、贈与税の対象になる。
この場合、基礎控除は年間110万円となる。
・契約者と受取人が同じ場合…所得税
・契約者と受取人が異なる場合…贈与税
3.所得税と住民税の負担が軽減される。
生命保険に加入していると、『生命保険料控除』の対象になる為、一定額まで所得税と住民税の負担が軽減されます。
学資保険のデメリット
1.途中解約すると元本割れのリスクがある。
特に、短期間での途中解約の場合、解約返戻金は0もしくはほどんど戻ってこない事が多いので注意が必要です。
途中解約する人は全体の10%以上いると言われているので注意が必要で
す。
2.満期時に元本割れリスクがある。
18年積み立ててきた資金の運用が上手く行かずに元本割れするリスクがある。
3.インフレに弱い。
教育費はインフレが非常に進みやすい分野です。
1990年以降の国立大の学費は1.6倍以上、私立大でも1.4倍もインフレを起こしています。
インフレが起こると言うことは相対的にお金の価値が下がる事を意味します。
インフレ率以上に利回りがないといくら預金するより学資保険の方が利回りがいいと言っても結果損をしてしまいます。
ちなみに、学資保険の年利回りは0.3%〜0.5%程度で、学費のインフレ率は1.1%〜1.7%前後なので学資保険で積み立てしてもインフレ率に負けてしまい、将来学資保険意外で資金を準備する必要が高くなります。
4.利回りが非常に低い。
高いもので0.5%程度しか利回りはありません。
中にはマイナス金利になるものもあります。
預貯金よりも利率が悪いものも多々あるので注意が必要です。

投資で教育費を準備する
総合的に見て学資保険はリスクの割りにリターンがほとんどないものが多いのが現状です。
せっかく子どもの為に18年間も積み立ててきて元本割れする事があったら目も当てられなくなりますよね。
そこでオススメなのが、学資保険ではなく投資で運用する事です。
毎月1万円を18年間貯蓄すると元本は216万円になります。
それに対して、毎月1万円を年利5%で運用すると349万円のなります。
実に、1.6倍以上の差になる事がわかります。
ただし、投資するのが怖いから学資保険で運用した方が安心だと思っている方も多いですが、実学資保険は集めたお金で保険会社が投資で運用しています。
それなら、保険会社に無駄な手数料を払わずに自分で運用した方がパフォーマンスが上がるのでオススメです。
最近は、学資保険が儲からなくなってきているので販売を停止している保険会社も出てきているのが現状です。
積み立ての投資商品に関しては、「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」や「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」など全世界に分散投資された物や現在世界経済を牽引しているアメリカ全体を購入する事ができる楽天VTIなどたくさん優良商品があります。
アメリカ全体を購入する事ができる投資信託を購入すると過去の実績では20年以上持ち続けると、どのタイミングで購入してもプラスのリターンが出たと言う超優良商品があります。
しかも、ジュニアNISAの制度改正があり非常に使い勝手がよくなりましたのでうまく活用して積立をしていけば学資保険よりいいパフォーマンスが出る可能性が高くなると思います。
投資の詳細に関しては今後記事にしていきますので楽しみにしてて下さいね。

まとめ
まずは固定観念を捨てる事が大切です
今回のお話で学資保険の利回りがいかに低くインフレに弱いかがわかって頂けたかと思います。
また、この記事が参考になったら幸いです!
次回も楽しみにしててくださいね。